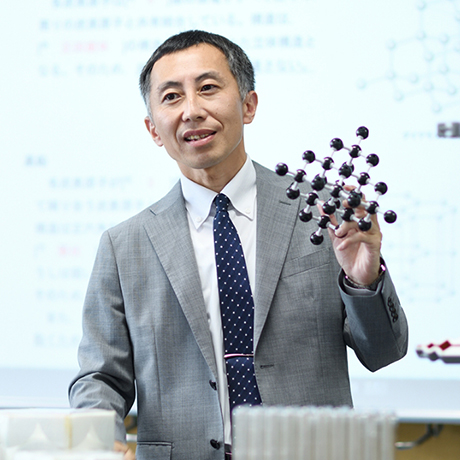学芸で高校時代を過ごした経験が、
教師としての糧になっています。
担当教科/数学 鈴木 愉宇 教諭

鈴木先生は浜松学芸高校でどんな3年間を過ごしましたか?
時間を惜しみながら、苦しみに耐えて一生懸命勉強したのかというと、正直そうでもありません。そうはいっても現代の生徒たちのようにスマホはなかったので、一人で静かに勉強をしたり、読書をしたり、楽器やパソコンで遊んだり、ものを考えたりする時間はあったのだろうなと思います。
高校時代、特に印象に残っている経験はありますか?
生徒会に携わったのは良い経験でした。私が入学したころは当時の諸々の事情により文化祭が「非公開・有志参加」という極めて小規模な形で開催されており、私も入学1年目は事情をよくわからず参加していませんでした。そんな中で高校3年生の頃から公開を再開することになり、生徒会としての企画を考えたり、事務的な作業ですが個々の展示場所を割り振るなど、前年までほぼやってこなかったいくつかの作業を行ったりしました。今思えば変化の大きいタイミングで関わることにより学んだことが多かったと思います。
友人関係や先生との関わりなどを含め、高校時代にどんな思い出がありますか?
当時の自分が所属していたコースは、授業をより多く行って学習の機会とする考えが色濃く反映されたカリキュラムで、たとえば夏休み前には8月10日くらいまで通常授業が行われるなど、たくさん学校に通っていました。その中で日々繰り広げられていた個性の強い先生方の授業は、今となっては良い思い出です。他にも、習熟度別授業が行われたり、提携する予備校の講師が一部の科目の授業を行ったりしていました。本校が「浜松学芸高校」という校名に変わり、進学校化していく黎明期であり、学校としても方向性を模索していた段階だったことが思い出されます。
また、前述したような流れとは別に、「漢字コンクール」という名称の「全校一斉漢字テスト」があったり、高2でクラスごとに体育祭での出し物を行ったりと、文系理系や進路希望問わず全員で取り組んでいました。こういったことは今の学芸にはなくなってしまいましたが、同級生と話すと当時の思い出として挙がります。
教師という仕事を選んだ理由を教えてください。
教師になることは幼いころからの夢というわけでもなく、親族に教員はいません。高校生や大学生の頃、自分が関わることで同級生・下級生・生徒が多少なりとも数学に前向きになれるというポジティヴな経験をしました。その後教育実習を経て、おぼろげながら教員として働くことのイメージがわき、現実的に考えていきました。振り返ってみれば、もともと自分にとって点数が取れなかった教科である数学を好きになっていったのは、先生方の関わりによってなされたところも大きかったです。
母校の教師になったのはどうしてですか?
本校で当時勤務されていた数学の先生が退職される時期だったのか、採用の可能性があるという状況でした。そこで「せっかくチャンスがあるなら挑戦してみよう」と思ったからです。
浜松学芸高校で高校時代を過ごした経験が、現在の仕事にどうつながっていますか?
私にとって浜松学芸高校の最初の印象は、「第1志望の公立高校入試に失敗して入学した学校」でした。当時はオープンスクールも今のように行われていたわけではなく、入試の時に初めて学校を訪れたと思います。公立高校入試のことは、自分自身の努力不足と、少しばかり運がなかったということだったと思います。
自分自身がそうした経験をしてきたことが、いろいろな思いを持って入学してくる生徒たちの気持ちが少しはわかることも含めて、自分自身の糧となっています。こうして20年も勤めているので縁があったのだろうと考えています。
担当の教科について、特に力を入れて指導していることを教えてください。
数学の基本的な語句や定石は、反復練習によって身につける部分が大きいと思いますが、どこまでもそれを続けることが学びであるとは思っていません。それらを身につけ、よく考えることが最も大切だと思っています。単なる問題の解き方だけにとどまらず、自分の書いていることは伝わるのか、答えは妥当なものか、なども含めてとらえてほしいと思います。
ショート動画のように「すぐわかって、すぐ面白い」ものが重宝される時代になっていると思いますが、そんな中でじっくり考えて、試行錯誤を繰り返しながら解に至る経緯を大切にし、時にはわからなさを面白がるような経験をしていただければ幸いです。
全員が数学の専門家になるわけではありませんが、以前に比べてさまざまな場面で数学的な素養が求められる時代になってきたと感じています。受験に必要かどうかという面だけで数学をとらえず、学ぶことの面白さを実感してもらいたいと思います。
3年間を通して生徒にどのような力を身につけてほしいですか?
「すぐに役立つこと」はすぐ役立たなくなってしまうこともあります。その一方で、たとえば「学び方」を学んでおくことで、何か新しいものに対応できるようになる。挑戦し、たとえ失敗してもそれを受け入れリスタートする経験をすることで、挑戦へのハードルを下げ、より多くチャンスをつかめるようにする。このように、具体的なスキルというよりはもう少し大きな枠組みで考えてもらえると、学ぶことに対する見方が広がったり深まったりするのではないかと思います。
改めて、浜松学芸高校にはどんな魅力があると思いますか?
本校は生徒の挑戦を受け入れ、応援する学校であると思っていますが、学校もまた変化し続けようとする姿勢を持っているように思えます。科やコースといった構造的な部分も、校則や生徒との関わりといった内面的な部分も、私が在学中の頃とは大きく異なっています。
本校は私立学校ですが、系列校がたくさんあるような大きな組織の一部としての学校ではなく、町工場・ベンチャー企業的な学校といって良いと思います。決して大きなスケール感を持っているわけではありませんが、意思決定のスピードが速く、小さなアイデアを、比較的素早く実行に移せる面があります。こういった面があるからこそ、生徒の動きに柔軟に対応し、可能な限り伴走し支えていけると私は思っています。
入学を検討している人に向けてメッセージをお願いします。
学校、特に私立学校には、それぞれ特徴があります。わかりやすい例でいえば、本校には現状、野球部も野球ができるグラウンドもありませんので、甲子園を目指そうと思っても厳しいです。一方、音楽・美術・書道の探究活動には普通科や探究創造科の生徒も参加していますし、その他文化系の活動は、もともと女子校だった頃に始まったものを中心に充実しています。今は私が高校生だった頃に比べて情報を入手しやすくなっていますので、よく調べ、可能ならば実際に訪れたうえで、進路選択を考えていただきたいと思います。